離婚時の財産分与の流れは?専業主婦ができるだけ多くの金額をもらう決め方

離婚を考え始めたの頃のわたしは、
「離婚をしたいけれど、10年も専業主婦だったわたしが、はたして夫から財産分与をもらえるのかしら?」
「購入したマイホームは、ローンを払ってきた夫のものになってしまうの?でも、独身時代のわたしの貯金も頭金に入れたのに・・・。」
などと、心配していました。
でも、そのような心配はまったく無用でした!
もしあなたが、かつてのわたしと同じように専業主婦であったとしても、財産分与として、婚姻期間中に夫が働いて稼いだお金の半分をもらうことができます。
昔の考え方と比べると不公平感を感じられる人もいるかもしれませんが、現在離婚をする夫婦の場合、専業主婦のほとんどが財産の半分を受け取っています。
このように、財産分与は、一般的な考え方とは異なる部分も多いので、今回は、
- 離婚するときの財産分与の決め方
- 専業主婦がより多くの財産分与を手にするにはどうしたらよいか
を中心にまとめていきます。
財産分与とは
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚する際に、それぞれの貢献度に応じて分けることをいいます。
民法にも、離婚する際には、相手方に対し財産の分与を請求することができると定めています。
離婚を急いでしまうと、もらえるはずの財産をもらわないまま離婚してしまうことになりかねませんので、しっかり取り決めをすることが大切です。
財産分与の種類
財産分与には、3つの種類があります
- 清算的財産分・・・ 夫婦が婚姻中につくった財産を清算する
- 扶養的財産分与・・・離婚により生活が困窮する元配偶者の扶養として
- 慰謝料的財産分与・・・不倫などで元配偶者を傷つけたことに対する慰謝料として
生産的財産分与
「結婚している間に、夫婦で協力して作ってきた財産は、その名義のいかんにかかわらず、夫婦の共有財産として、離婚の際にはそれぞれの貢献度に応じて公平に分ける」という考え方です。
離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けるということです。
そのため、不倫などで離婚原因を作ってしまった側からの請求でも認められます。
扶養的財産分与
離婚により、夫婦の片方が生活に困窮してしまう場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により分与される財産のことです。
高齢や病気であったり、専業主婦である場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的です。
慰謝料的財産分与
不貞行為など離婚原因により、慰謝料の請求が問題になることがあります。
慰謝料は、財産分与とは意味合いが異なるので、本来別々に算定するのが原則です。
しかし、両方とも金銭がかかわる問題ですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずに、まとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることがあります。
財産分与の対象となる財産とは?

財産分与をする場合、まずは、財産分与の対象となる財産にどのようなものがあるかをチェックすることが必要です。
財産分与の対象となる財産を見落としてしまうと、後になって「損をした!」という結果に。
具体的には、財産分与の対象となる財産かどうかについて、次のように考えられています。
対象となる財産
プラスの財産
現預金、有価証券、出資金、退職金、年金、生命保険、学資保険、不動産(自宅)、自動車、家具、家電など、夫婦で協力して婚姻中に取得した財産 は、対象になります。
マイナスの財産
プラスの財産だけでなく、住宅や車のローン、学資ローンなど、婚姻生活のためにできた負債(借金)も財産分与の対象になります。
子供名義の財産
子供名義の預金は、お年玉など子供自身が他の人からもらったものが預けられているものは、財産分与の対象となりません。
しかし、子供名義で積み立てていた場合には、財産分与の対象となることがあります。
子供にかけた学資保険も、夫婦で働いた給与などから保険料をかけているのであれば、一般に財産分与の対象と考えられています。
個人自営業者の事業用資産
個人自営業者の場合は、事業用の資産、負債も財産分与の対象となります。
対象とならない財産
結婚前の財産
独身時代の預金、花嫁道具として持ってきた家具などは夫婦で協力して作った財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。
結婚前から持っていた住宅や車でも、結婚後にそのローンを返していたような場合には、結婚後のローン支払い相当分は、財産分与の対象となります。
結婚後に相続・贈与を受けた財産
結婚している間に、親からの相続や贈与を受けた財産は、夫婦で協力して作った財産ではないので、財産分与の対象になりません。
また、「結婚指輪や婚約指輪 は財産分与の対象になるのか」とよく聞かれますが、いずれも財産分与の対象にはなりません。
離婚するからといって、法的に返さなくてはならない物にはなりません。
夫婦のプラスの財産とマイナスの財産がある場合には、プラスがマイナスを上回る場合に、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分けるのが一般的です。
プラスにもマイナスにも大きくかかわるのが、不動産。
不動産の金額については、夫婦で査定金額が異なり、分与の金額が変わってきてしまうことがあります。
少しでも分与金額を増やすためにも、高く売ってくれるところで査定をお願いするのもいいかもしれません。
ちなみに、こちらは、実際にご相談者様が相場より高く売れたとおしゃっていた査定会社です。
大手の野村不動産なので、安心感もありますね。
財産分与の割合

財産分与の対象となる財産がわかったら、次にどのような割合で財産分与をするのかを見ていきましょう。
原則は2分の1
財産分与の割合は、財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点を見て決めていくことになりますが、基本的には、結婚後に作った財産を合算して折半します。
ですから、たとえ夫だけに収入がある専業主婦の場合であっても、「夫は会社で仕事をし、妻は家で家事をした」ということから、原則的に2分の1ずつと考えられています。
例外
しかし、医師など専門的技術によって収入を得て夫婦の財産が作られた場合は、例外的に財産分与の割合が半分ではなく、その専門性を得た努力等を考慮して、分与の割合が修正されることもあります。
財産分与の対象となる期間
財産分与の対象となる期間は、婚姻時を起点に、夫婦の協力関係が終了する別居時を終点とするのが一般的です。
財産分与の決め方と流れ

財産分与は、次のような流れで決めていきます。
夫婦での話し合い
まずは、話し合い(協議)によって財産分与を取り決めることができるのであれば、一番理想的ですね。
財産分与は、お互いが納得すれば、当事者の合意によって自由に決めることができます。
- まず、財産分与の対象となるもののリストを作る
- 次に、リストをもとにどちらがどの財産をもらうのかを話し合う
このように、話し合うことができればいいのですが、お互いが譲り合うことができないと、決めることは難しくなってしまいます。
調停
調停で決める場合は、①離婚調停時に一緒に話し合う方法と、②離婚成立後に財産分与請求調停で話し合う方法があります。
離婚調停については、こちらもご覧くださいね。
裁判
もし、離婚調停において財産分与についての話し合いがまとまらない場合は、離婚訴訟を起こすことになります。
離婚裁判の中で、離婚と財産分与について決めていきます。
裁判離婚をするには離婚原因が必須
裁判離婚をするためには、具体的には以下の事由に該当しなければなりません。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚裁判の手順
- 訴状の作成
- 裁判所への訴状の提出
- 相手への訴状の送付
- 第一回口頭弁論期日の決定
- 数回の弁論準備や口頭弁論
- 判決
通常、1年から1年半くらいの期間で結審します。
裁判では、話し合いや調停の場合と異なり、証拠がとても大切になります。
先に挙げた、財産分与の対象なるもののリストや相手の給与明細や財産を証明するものをきちんとそろえておきましょう。
専業主婦が財産分与を有利に進めるには?
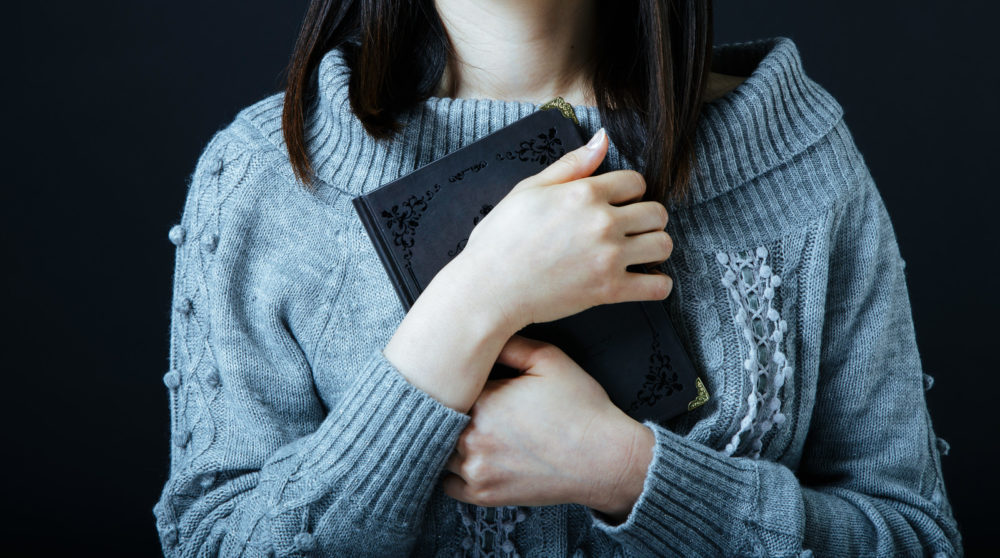
財産分与を有利に進めるためのポイントは次の2つです。
- 相手名義の財産を明らかにすること
- 自分名義の財産の内、結婚前からの財産、相続や贈与により得た財産を明らかにすること
結婚後に稼いで作った相手名義の財産が多いほど、結婚後に稼いで作った自分名義の財産が少ないほど、もらえる分が多くなることになるからです。
財産分与の証拠を集める
財産分与を有利に進めるためには、相手が隠し持っている財産がないかチェックすることが重要です。
そして財産をチェックしたら、その財産があることの証拠を集める必要があります。
例えば、
- 配偶者の預貯金通帳(または通帳のコピー)
- 所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類)
- 不動産登記簿
- 生命保険に関する書類
- 証券口座の明細
などがあります。
財産分与の証拠集めは、離婚が決定的になる前に調べておくことがとても重要です。
配偶者が財産を隠していることも多々あります。
その場合の対処法は、こちらで解説しています。
専業主婦が財産分与をより多くもらうために
財産形成への貢献度の主張
まずは、あなたが夫婦の財産形成に大きく貢献したことを主張しましょう。
財産分与の相場は基本的には2分の1とされていますが、もちろん例外もあります。
夫婦の協力関係が無い期間があったり、折半することにより、不公平な事情があれば説明すべきです。
たとえば、
- 家族を置いて家出していた
- 刑務所に入っていた
- 単身赴任中まったく連絡が無かった
などがあります。
過去のわたしの事例で言えば、元夫が、息子とわたしを置いて年間3分の1は家を一方的に出て行ってしまっていたことが考慮されました。
財産分与対象外の財産の形成への貢献度の主張
本来財産分与の対象にならない財産の形成に貢献したと言えるときにも、財産分与を有利に進めることができます。
例えば、
- 不動産を相続したときに、結婚後の貯金から相続税を支払った
- 結婚前から所有していた家を、結婚後の貯金を使って修繕した
などです。
生活費がこんなにかかるはずがないと言われたら
家計を管理していなかった側から、生活費がこんなにかかるはずがなく、へそくりがあるのではないか、と言われることがよくあります。
特に、専業主婦の方に多いようです。
わたしも言われました(笑)
家計を管理していた側からしてみると、「一生懸命やりくりしてきたのに!」と憤慨することでしょう。
調停の場合は、調停委員から説明を求められることがあります。
調停委員は、相手の味方をして言っているというよりは、話を進めるために求めていることが多いようです。
相手の収入と支出のおおまかな内訳(食費、医療費、学費、光熱費など)をできる範囲で説明しましょう。
まとめ
今回は、
- 離婚するときの財産分与の決め方
- 専業主婦がより多くの財産分与を手にするにはどうしたらよいか
についてお伝えしました。
財産分与は、離婚と同時に決めることが一般的です。
離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合でも、離婚後に財産分与を請求することは可能です。
ただし、離婚したときから2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です。
離婚とともに、財産分与についても計画的に準備をしてくださいね!


